ご近所を中心に対象エリアとした事例
二子げんきかい(サロン)
- ①
- ②
- ③
- ④
活動の概要
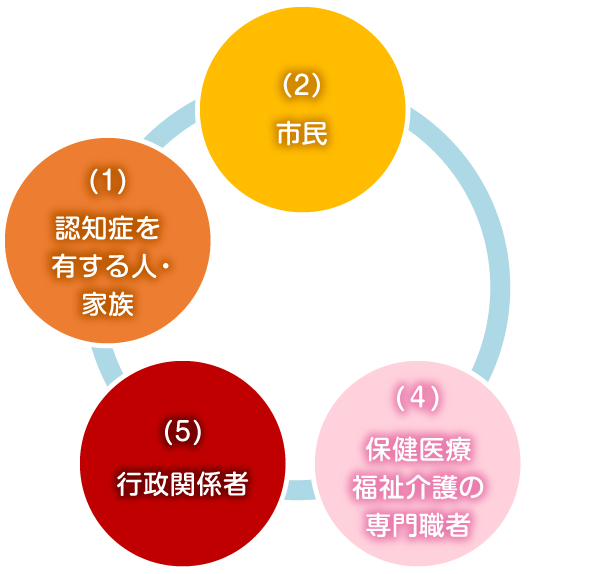
活動の場・範囲
一地区(約130世帯)の65歳以上の住民(約90人)が対象だが、隣接地区の住民も参加できる。
活動のきっかけ
有志の食事会で、保健師から「地区全体の地域づくりの場としてやってみませんか」と声がかかった。
活動の目的
「元気かい?」とみんなで集まり、お互いの健康を確認する。みんなで集まって健康づくりをする。
専門職の関わり
活動開始の動機付け、継続支援、専門職と参加者・住民同士をつなぐ、会に出向き相談をうける。
協働のポイント
- 一人ひとりの「出番」を大事にして、参加者のできることを出し合って活動する
- 一緒に活動内容を考えて運営する仲間をつくる
- 参加の仕方は人それぞれ、誰もが居心地よく、「来てよかった」と思える
- 地区の代表者や老人会にも、サロンの活動の承認を得る
活動の経過と内容
- 元保健推進員を中心に有志8名で始めたサロンに、地域包括支援センター保健師が参加した。地域づくりについて意見交換したことをきっかけに、地区全域を対象とした通いの場の立ち上げを検討しはじめた。
- 元保健推進員と地域包括支援センター保健師が、老人会長・区長に説明し協力を得た後、第一回を開催し、参加者は17名であった。
翌年には参加者の希望で、毎月2回に活動を増やし、毎回10~15名が参加している。 - 活動の年間予定は、元保健推進員とサロン参加者、地域包括支援センター保健師が話し合って決める。元保健推進員だけでなく、サロン参加者も誘って運営に関わってもらう。
- 参加者それぞれが、料理や手芸、マジックなど好きなことや得意なことを持ち寄る。
居心地の良い楽しい場づくりができ、引っ越してきた人も含めて、参加者は増加している。 - 専門職はサロンについて、健康づくりの場・介護予防の場であるとともに、専門職を含めた学びの場であると捉え、専門職と住民・住民同士をつなげている。
また、困っている人が、早い段階で相談できる場だと捉えている。
専門職と市民等との協働の方法
参加者と一緒に活動を考えて、誰もが「来てよかった」と思える
- 参加者からも運営者を募って、みんなで一緒に活動を考えるから心強い、楽しくなる。(世話役住民)
- 大事なのは、みんなが「今日も来てよかった」と思うこと。みんなが楽しんで、サロンが続かないと意味が無い。(世話役住民、専門職)
- 以前から地域を支えてきた老人会や地区会に説明し、サロンを認め協力してもらう。(世話役住民)
参加者ひとりひとりの「出番」を大事に、得意を活かして、みんなを誇らしく思う
- 高齢者も、いつも人にやってもらうのではなく、自分の得意を活かす「出番」をもつことを大事にしたい。そうすると、参加者がいきいきする。(世話役住民)
- 昔からの知り合いだけでなく、新しく来た人にも得意なことを聞いて、活動に活かす。(世話役住民)
- 参加者全員の存在がありがたい。ちょっとした食べ物や手芸品の提供もすばらしくて誇らしい。(世話役住民)
立場にこだわらず、それぞれによって居心地よいように、参加の仕方は一人一人に任せる
- 参加者みんなに個性がある。参加者みんなに任せれば、自然と交流が始まる。
参加者が順番に話す機会を設けると、好きなことや特技、日課が共有され、自然と次の活動や交流につながる。(世話役住民) - 専門職や住民といった立場にかかわらず、みんなが楽しい活動をする。(世話役住民)
活動の成果
参加者が自分らしく楽しくいられる場であり、活動を知った人の地域づくりへの関心が高まる
- 参加者は様々な背景や健康状態があるが、自分らしく楽しく参加している。
- 他の地区の住民から、「うちでもやってほしい」という希望があがる。
参加者が制度やサービスにアクセスしやすくなる
- 参加者が、活動のなかで自分の変化を感じると、受診につながりやすい。認知症外来や介護保険等の支援につながりやすい。
地域づくりの拠点として、ケアネットワークの拡充に貢献
- 様々な背景を持つ住民同士、専門職同士、住民と専門職がつながる場となっている。
- 地域の専門職から「ぜひ貢献したい」と声が上がり、講師や参加者として協力がある。


