自治会地区・住宅地区を対象エリアとした事例
東千葉和・輪・環の会(住民グループ)
- ①
- ③
- ④
- ⑦
活動の概要
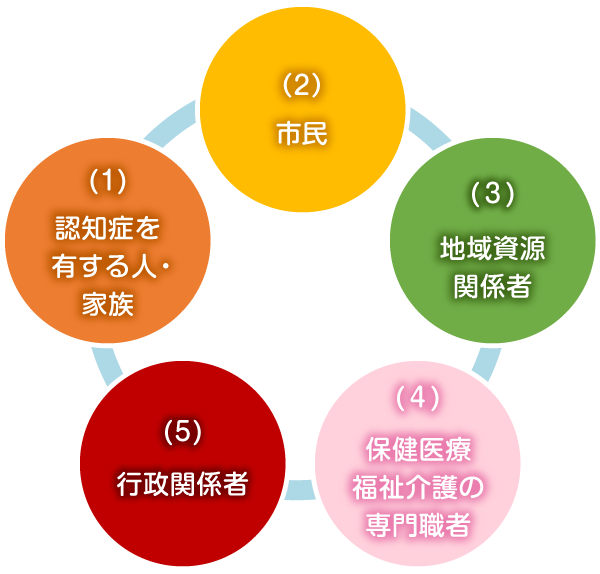
活動の場・範囲
5自治会による自治会連合会(約1000戸、約3000人)が基盤で、自治会集会所を拠点に活動。
活動のきっかけ
自治会役員経験者で約10年間ボランティア活動をしていたところ、既知の行政職員から大学教員を紹介され話し合いをしたこと。
活動の目的
最期まで自分らしくこの地域で暮らし続けたいを旗印に、健康増進のための活動や安心した生活のための交流やネットワーク作りをすること。
専門職の関わり
活動が軌道にのるための支援と、情報提供や相談。
協働のポイント
- 皆の共感をうみ、納得のいく活動をする
- なんとなくの思いを具体的にして、行動に変える
- 自分達の立場で自分達にできることを皆で共有して、協力しながら具体的な形にする
活動の経過と内容
- 活動開始の10年前から、自治会経験者の仲間づくりの会があり、趣味やこの地域に住み始めた理由など親睦を深め、地域通貨を使ったボランティア活動をしていた。このグループと行政と大学が出会ったことをきっかけに、各々が「新しい何かができるかもしれない」と期待感を持ち、住民、大学、行政のパートナーシップにより住民主体の地域包括ケアを具体化する行動を開始した。
- 最初に、三者の協働で住民アンケートを行い、地域の現状を住民と共有するところから開始した。住民が抱えている思いや将来への不安が顕在化したことが活動のスタートを後押しした。
- キックオフ会議の後、ワークショップを重ね、個々がグループで話しあった意見をまとめ、全体の活動に反映させたものを個々が確認するプロセスで、住民の意欲・活力が増していった。
- 住民フォーラムで活動の報告と今後の方向性を各活動グループが発表し、フォーラム後にそれぞれにやってみたいことを軸にグループを作り、企画や年間計画を立てた。
- 健康増進活動、介護の勉強会、若い世代との交流、地域情報誌など8つの内容のプロジェクトができたので、そのプロジェクトを進めていく活動体制を整えた。
専門職と市民等との協働の方法
新しいわくわくする活動をしようと考える
- 10年先のことを考えた時にこのままでよいのかという疑問を潜在的に持っていた。行政職員と教員の働きかけによって、何かが開きそうというようなみんなの意気込みみたいなのがあったような気がする。(住民リーダー)
この地域で暮らしていく上での現状と課題をみんなで共有する
- 講座では大学の3人の先生がそれぞれの立場から地域を見て捉えたことを話してもらった。その中で、住民が抱く地域の中の特徴を、自分が話をさせてもらって、まずはこの地域の現状を共有しようというところから、この会が始まった。(住民リーダー)
住民が主体で、住民の中に解決の糸口があると信じる
- 行政が押し付けるのではなく、なるべく住民主体で、専門家が教えるものではなくて、答えは住民の中にある。住民が思っていることを具体的に地域の中で協働して取り組めれば、課題解決になると思っていた。(行政職員)
仲間意識をもって、頼りになる関係をつくる
- 大学の先生も、行政の職員も各グループの中に入って話し合った。そうすると、参加者は先生や行政職員のアドバイスを自然に聞き、教えてもらえるので、そこで仲間意識ができ、やらされ感は全く出てこなかった。メンバーの一員で、しかも専門家だから、すごく頼りになる、そういう関係が出てきた。その意識はみんなで大事にして進めていこうと、最初の頃は結構話ししたりした。(住民リーダー)
「自分達の立場で自分達にできることをする」を活動の前提として協力する
- 補助金があって何か成果を出さないといけないわけではなかった。目指すところ「最後までこの地域で自分らしく暮らしていきたい」は決まっていたけれど、具体的な着地点が見えない中でまずは自分達でできることをという気持ちで活動を開始した。(行政職員)
活動の成果
介護保険サービスに対する関心の高まりと行動
- 専門家による介護保険をテーマにした学習会を受けて、住民自身が地域の介護保険事業所や医療機関を回って情報を集め互いに情報を共有し、地域に情報を提供するという動きになった。
見守り合う地域づくりの促進
- 本会メンバーから希望があり、認知症高齢者対象の「見守り・体験会」事業の開催を、住民グループの「あいさつ運動」と組み合わせ、高齢者の徘徊対策というよりも、「あいさつをする地域づくり」というコンセプトで、地域包括支援センターと住民グループが共同で「地域の見守り声掛け体験会」を開催した。
あいさつロード運動が始まり、地域で認知され、子どもの登下校の見守りを行う。



