自治会地区・住宅地区を対象エリアとした事例
ベイタウンかふぇ(認知症カフェ)
- ①
- ②
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
活動の概要
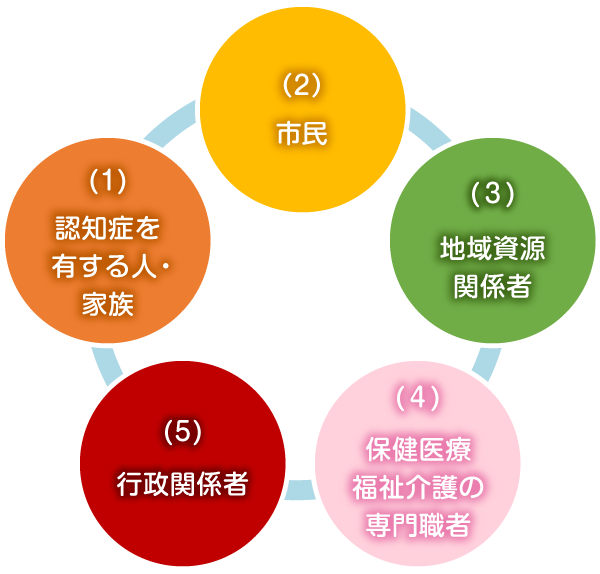
活動の場・範囲
地区の街区型集合住宅群に居住する住民が対象だが、隣接地区の住民や関係者も参加できる。
活動のきっかけ
認知症になっても安心して暮らせるまち作り活動の事例を知り、自分達のまちもそうありたいと、まちに住まわれている当事者・ご家族(介護・介助者)との接点をもって実態や課題などの把握をはじめたこと。
活動の目的
当事者や介助・介護者の立場から、認知症について理解を深めると共に、まちの人々が身近に知り語り合える場を地域に作ること。
専門職の関わり
参加者(当事者やご家族)や接点を持つ世話人からの相談をうけ、助言やより専門担当への紹介(リファー)などにより、専門職と参加者・住民同士をつなぐ。
協働のポイント
- 想いや変化をとらえ、違いを認め合いながらもそれぞれが楽しめることを大事にする
- それぞれの得意や専門性・知識や経験を活かして安心して暮らせるまちづくりをする
- 専門職などの立場を超え、お互い様の気持ちを持って、認知症になったときにどう生きるか、どう関わるかを仲間と共に考え学びあう
活動の経過と内容
- 2015年、後に会の世話人となる認知症家族の介護経験や専門家、まちづくり経験がある有志3名が中心となり、自発的な地域住民のボランティア団体を発足させた。医療や介護の専門職アドバイザーの助言や協力を得て、多くの住民参加による意見交換やワークショップを行いまちの生活者ニーズを把握すると共に、このような活動への共感・協力者と出逢うことができた。
- 2017年、民間助成金を獲得し、地区にはじめての認知症カフェをオープン。介護の経験のある者、ボランティア仲間、介護の専門職たちが世話人となり、認知症の人と介護家族、認知症に対する不安をお持ちの方などの居場所とした。月1回開催し、初年度から年間のべ600名を超える参加があった。
- 参加者に楽しくなごみ対話や関係性が進んで欲しいという思いから、ミニコンサートや落語、簡単なものづくり、講演会などたくさんのイベントが充実していった。さらに、スタッフや地区住民の様々な得意なことや好きなことを持ち寄って交流ができるコミュニティスペースがうまれた。
- 活動を続けていくうちに専門職の参加も増えた。専門職は、住民やスタッフの相談にのるだけでなく、立場を超えて共に楽しみ語り合い、学びあえる場と捉えている。
- コロナ禍では、計画が実施できないなどの危機があったが、新たな民間助成金を得て環境配慮の装備充実や、行政や関係者、他活動地域とオンラインネットワークを活用した対話や学習なども行い交流を続けた。
- 企業や行政などと協働し、活動がさらに多彩に発展している。
専門職と市民等との協働の方法
認知症の人も介護者も誰もが楽しめる配慮や啓発が大事
- 活動に参加することで仲間ができて楽しいし、楽しく、またかかわりたいと思わないと継続しない。(世話人)
- イベント中心となって本来の目的からずれることがある。常に振り返りをして、認知症ご本人やご家族の人も楽しめ、介護者の癒しとなるような配慮や啓発活動が大事だと思う。(世話人)
参加者ひとりひとりの想いや老いによる変化をキャッチすることを大事にする
- メンバーの思いや希望を実行し評価することを繰り返すことを大事にしている。(世話人)
- 参加者の老いによる意識や行動、家族や知人とのかかわり変化に注意していくことを大事にしている。(世話人)
認知症になったときにどう生きるかを仲間と共に考え学びたい
- 専門家に話を聞いてもらって気持ちが楽になったとき、まちの中にも同じような困りごとを持っている人がいると考えた。(世話人)
- 自分たちが認知症になったときにどう生きるか、その時家族はどうなのか、などを共に考え学びたい。(世話人)
専門職の立場でなく住民として地域で関わりたい
- 看護職としてではなく地域に入り込んで一緒に関わっていきたい。(世話人)
お互い様の気持ちを持って認知症になっても安心して暮らせるまちづくりがしたい
- 認知症を恐れずに隠さなくてもよいものとして安心できるまちづくりがしたい。(世話人)
- いつサポートを受ける側になるか分からないので、お互い様の気持ちで活動している。(世話人)
認知症の家族を介護した経験から、地域で協力できることをしたいと思う
- 認知症の家族の介護の経験から、地域で協力できること、自分の得意や経験を活かせるがあるのではないかと考えた。(世話人)
活動の成果
参加者の増加やコミュニティスペースの設置により活動が発展しケアネットワークが拡充
- 参加者それぞれの思いを集約し実行することを通して、参加者が増えたり力のある参加者が協力してくれたりして活動が大きくなった。
- コミュニティスペースが得意とすることの実現や行事などを発信できる場所、誰でも来られる場所として発展した。
専門職に気軽に聞けることやコミュニティスペースにいつでも行けることで制度やサービスへのアクセスが向上
居場所ができたことで認知症の本人や家族のwell-beingに貢献
- 居場所ができたことで好きなときにおしゃべりができるようになった、そこに行くと誰かがいて安心できる時間になる。
- 心が休まったり、介護経験のある家族や専門家に話が聞けたり気軽に相談するなど、心強い場所。


