�q�������@�y���E�W�F�[���E�{�}�[�搶�����Љ�����܂��B
�@�搶�ɂ͌��ݐ�t��w�q�������Ƃ��āA�Ō�w�����Ȃɂ����āA���m�O���ے��̊w���ɁuFamily Nursing�v���A���m����ے��̊w���ɁuCommunity based nursing research�v���A�����āACNS�����R�[�X�̊w���ɂ́uAdvanced Nursing�v�����u�`���������Ă��܂��BLearning Circle ��p���������@�ŁA�e�N���X�Ƃ�����M�S�ȍu�`���W�J����Ă��܂��B


������
| 1970�N |
|
�č��I�n�C�I�B���A�N������w�Ō�w������ |
| 1972�N |
|
��I�n�C�I�B�@�P�[�X�E�E�F�X�^���E���o�[�X��w |
|
|
�t�����V�X�@�y�C���@�{�[���g���Ō�w���@�C�m�ے��C�� |
|
|
�Ō�w�C�m�@��U�@�ꐫ�Ō�w |
| 1982�N |
|
�č��I�n�C�I�B���A�N������w�ɂā@ |
|
|
Ph.D(Family Ecology and Educ. Administration) �擾 |
| 1983�N |
|
�T���f�B�G�S��w�t�B���b�v Y.�n�[���Ō�w���@�Ƒ��Ō�w���� |
| 1994�N |
|
�C�[�X�g�J�����C�i��w��q�Ō�w���� |
| 1996�N |
|
�m�[�X�J�����C�i�B����w�E�B���~���g���Z�Ō�w������ |
| 2001�N |
|
�m�[�X�J�����C�i�B����w�E�B���~���g���Z�Ō�w���������w���� |
| 2008�N |
4�� |
��t��w�Ō�w���q������ |
|
6�� |
�m�[�X�J�����C�i�B����w�E�B���~���g���Z�Ō�w�����_���� |
 |
��Ȏ�ܗ��Ȃ�
| 1972�N |
|
�V�O�}�E�Z�^�E�^�E���ۊŌ�w�� |
| 2004�N |
|
Family Nursing Scholar Award ��� |
 |
��Ȓ�����
�@Bomar,P.J.(2004) Promoting Health in Family(3rd ed.) :Saunders.
���̖{�́AAJN��Editor and author Award����܂��Ă��܂��B�܂��A�č������łȂ��A���{�A�u���W���A�J�i�_�A�C�M���X�̏C�m�ے��A���m�ے��Ŏg�p����Ă��܂��B


�Ȃ��@Family Nursing�@�ɋ����������ꂽ�̂ł����H
�@30���N�O�A�A�N������w�ɑ�w�@�C�m�ے�����鎞�ɂ́A�܂��@Family Nursing�̃R�[�X�͂���܂���ł����B�S�Ăł�2��������Family Nursing�̃R�[�X�͂Ȃ��A������l�����Ȃ��������߂ł��B���͕ꐫ�Ō���U���Ă��܂������AHealth Promotion�@�ɋ��������������ƁA�����āA������N��̐l��Ώۂɂł��邱�Ƃ���AFamily Nursing�̒S���ɖ����������܂����B�����Ō�A���l�Ō�̋��������Ƌ��͂��āA�R�[�X���J�݂��܂����B
�搶���������ɂȂ����{�ɂ��ċ����Ă��������B
�@�����w�ŁA�u���ȏ��������v�ƍ����Ă����Ƃ���A�o�ŎЂ���u�搶���������ɂȂ�����ǂ��ł����H�v�ƒ�Ă�����܂����B�ŏ��́u���[���v�Ǝv���܂������A�{�̓��e�⍜�q�����߂�ƁA���ꂼ��̌��e�������K�C�҂��A�o�ŎЂ��A�����J�A�J�i�_����T���Ă���āA���ł́A��3�ł��o�ł���Ɏ���܂��B���̖{�̒���Family Nutrition�ɂ��ď����Ă��ꂽ�̂́A���̍ŏ���Family Nursing�N���X�̑�w�@���ł��B�ޏ��́ANutrition�̐��Ƃł����B���Ƃ�i�߂čs�����ŁA�ޏ��͉Ƒ��̒��ɂ�����Nutrition�̏d�v���ɋC�t���āA������A�����̌����e�[�}�ɂ�����ł���B
���{��|��ł��o����邲�\��́H
�@�v��͂��Ă��܂��B�����A�|�邾���ł͂Ȃ��A���{�̉Ƒ��ɂ��Ă��A���荞�݂����ł����A���e�����{�̉Ƒ��̌���Ƀt�B�b�g����悤�Ȃ��̂ɂ������̂ŁA
�����������Ԃ�������Ǝv���܂��B
�Ō�ɓ��{�̐��Ō�t�Ƀ��b�Z�[�W�����肢���܂��B
�@Research supports that families are where health promotion and disease prevention is taught, supported or undermined. Therefore, Clinical Nurse Specialists of Japan are encouraged to include families in all aspect of nursing care for individuals, families and communities beginning with assessment of the problem or issue and ending with evaluation of the intervention.
�i2008�N6���j

�u���Ō�t�̂��߂̍ŐV�a�Ԋw�v�̍u�t�A���א搶�����Љ�܂�
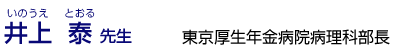

���{�a���w��]�c���A���{�a���w��F��a����A���{�����g��w��F�����A���{�Տ��זE�w��F��זE�f����B��w���m�i������w�j�B
�����F�w�i�[�X�E���C��E�R���f�B�J���̂��߂́@�Ȃ�? ���Ȃ�ق�! �a�Ԑ����G�����[�~�i�[���x���f�B�J�o�ŁA2008
�w�w���̂��߂̎��a�_�@�l�Ԃ��a�C�ɂȂ�Ƃ������Ɓx��w���@�A2001
�w���ꂾ���͒m���Ă����������a�̐��藧���x��w���@�A2000
�w�����g������a�w�x��]���i�����j�A1996
�w�ݑ�P�A�[�ւ̃A�v���[�`�@�K��Ō�̊m�����߂����āx��w���@�i�����j�A1988

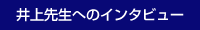
����ȕa�Ԃ��킩��₷���u�`���Ă��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B����S���ꂽ�_�������������������B
����@��S�Ƃ������C�����Ă���_�́A����̃��A���e�B�𗍂߂ĕa�Ԃ�������邱�Ƃł��B�����N���邩������Ȃ��̂���Â̌���ł�����A�����̎v���ʂ�ɂȂ�Ȃ����Őv���ɔ��f����Ή����K�v�ƂȂ�܂��B������A�ǂ̂悤�ȏł����炪�p�j�b�N�ɂȂ�Ȃ����߂̒m���̏K���Ɗw�K���d�v���ƍl���Ă��܂��B�����ЂƂ́A�������`���������Ƃ��Ȃ�Ƃ��w�ю�ɗ������ė~�����Ƃ����v���ł��B���̂��߂ɁA���ꉻ�o���Ȃ�������⊮����G��`���Ă��܂��B����͈Ӑ}�I�ȊG�ł�����A�|�p�Ƃ��`����̂���G�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�o��������U�w�ɂ̂��Ƃ������m�Ȑl�̂̍\���̊G�ɂ������܂��B
�G���A��ςɑf���炵���ł��B
����@�f���炵���ƌ����Ă��������ċ��k�ł��B���̕`�����̂͒P���ȓ��̊G�ł��āA�]���Ȃ��Ƃ���؏Ȃ������̂ł��B
�`���������Ƃɒ����ɕ`���Ă���Ƃ������Ƃł��ˁB
����@�����ƌ����킯�ł͂���܂��E�E�E�B���͈�A���̊G�������l���A�����g���Ӑ}��������ŗ������Ă���邩�ł��B���������Ӗ��ŁA�ʐ^�ł͂Ȃ��P���ȊG�ɂ͂������܂��B
�w�Ȃ����Ȃ�قǕa�Ԑ����[�~�i�[���x�̎O�N�ԘA�ڂŏo�ŎЂƂ̘A���������A�M�S�ɂ��ꂽ�ƕ����Ă��܂��B
����@�������ł́A�ʏ�1���肹������4�y�[�W�̂Ƃ�����A6�y�[�W�Ɋg�債�ĘA�ڂ��܂����B�G���`���Ă���̂ŁA�ǂ����Ă��y�[�W��������Ȃ��Ȃ�܂��B�o�ŎЂ̃X�^�b�t���H�v���Ă���܂����B
�@���̃e�L�X�g�́A�Ō�t�����̒ʏ�̃e�L�X�g�������Ȃ背�x���������A�[�����e�ɂȂ��Ă��܂��B�a�Ԑ������܂ފ�b�Ȋw�̋���ɂ����āA��t���w�Ԃ��ƂƊŌ�t���w�Ԃ��Ƃɍ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��邩��ł��B������A�u����͊Ō�t�͒m��Ȃ��Ă����v�Ƃ����悤�Ȕz���͂��܂���B�����ł킩�����悤�ȋC�ɂȂ�m���́A��Ì���Ŏg�����ɂȂ�܂���B
�@�蒅�������m���������A�����܂ł����҂̗���ɗ��A���҂��댯�ȕ����Ɍ����������Ȃ�A�������|�߂�B���̂悤�ȊŌ�t����l�ł���������ė~�����ƔO���Ă��܂��B���̎v�����Ȃ���A���̂悤�ȋ��ȏ����������Ƃ��Ȃ��A�Ō싳��Ɋ֗^���邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B
�Ō�ɁA���Ō�t�Ɋ��҂��邱�Ƃ������������������B
����@��قǏq�ׂ����ƂƏd�Ȃ�܂����A�����܂ł��a�߂�l�̗���ɂ������m���Ɨ��_�������A��Z��g�ɂ��A������s�����ł��邱�Ƃ����҂��܂��B
�@��ÂƂ����ꂪ�A�͂��炸���a�C��S���Ă��܂�����l�̐l�ԂƂ̑Λ�����n�܂�Ƃ���������O�̎�����Y��Ȃ����ƁB�����āA���̈�ÂƊŌ삪�A��t�E�Ō�t�E�p�����f�B�J���Ƃ����������̃X�^�b�t�̍s������\�z����Ă��邱�Ƃ�F�����邱�ƁB���̊�Ղɗ����A�Ō�t�Ƃ������̈�������������A���҂ɂƂ��āA���Ƃ��ė��s�s�Ǝv���錾����������t��p�����f�B�J���X�^�b�t�ɑ��������Ƃ��A�����ɁA�B�R�Ƃ����ԓx���Ƃ����Ō�t�ɂȂ��Ƃ��B
�@�a�߂�l�Ԃ��x���ł���Z�p�_�i�e�N�m���W�[�j���������肵�Ă���A�l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����������o���q���[�}�j�Y���́A�����ƌォ����Ă�����̂ł��B
�M�d�Ȃ��b�����A���肪�Ƃ��������܂����B
 |
| �u�`�̗l�q |
�i2008�N5���j

�u���Ō�t�����R�[�X�v���n�܂�܂���
�@����20�N�x4�����u���Ō�t�����R�[�X�v���J�n����܂����B�{�N�x�̓R�[�X��2���A�Ȗڗ��C��2�������w���A4�����猻�݂܂łɁu���Ō�t�̂��߂̍ŐV�w�v�u���Ō�t�̂��߂̍ŐV�a�Ԋw�v�����āA�q������Dr.Bomar�ɂ��uAdvanced Clinical Nurse Specialists�v����u���Ă��܂��B8����UCLA Medical Center�ōs�Ȃ�CNS���C��O�ɁA�l�C�e�B�u�u�t�ɂ���w���C���J�n����Ă��܂��B
�@�{�N�x�́A���s����̉^�c�ɂȂ�Ǝv���܂����A�{�R�[�X�̖ړI�ƏƂ炵�Ȃ��疲�ƔM�ӂ������Ď�g��ł��������Ǝv���܂��B�i�v���W�F�N�g���[�_�[�@�����L�}�j
 |
| 4���̎�u�J�n��O�ɃR�[�X�̊w���A�����ƂŁA���b����J���܂����B |
�i2008�N4���j
|