附属センター
ページへ移動する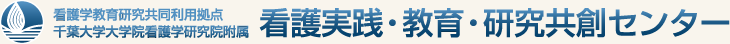
当センターは、看護学が独自の教育研究分野を確立しつつあった昭和50年代半ば、看護系大学の教員等、看護学分野の調査研究に従事する者、指導的立場にある看護職員の共同利用に供することを目的として、1982年4月に千葉大学看護学部に付置センターとして設置されました。設置当時の社会情勢に鑑み、当初組織は、継続看護研究部・老人看護研究部・看護管理研究部の3研究部構成でした。その後、急速に進展する少子高齢化社会とその看護ニーズに応える看護ケア開発を促進するため、老人看護研究部をケア開発研究部と改称しました。さらに、保健・医療・福祉制度の改革に伴う看護職者の役割拡大に関わる政策研究やキャリア開発を促進するため、看護管理研究部と継続教育研究部を発展的に統合し、政策・教育開発研究部が発足しました。さらに、2021年、看護学研究科が看護学研究院へと改組され、教育組織と教員組織を分離する組織改革が行われました。以降、当センター固有の教員組織はなくなり、コア・メンバーを中心とする看護学研究院全教員がセンター事業に参画するようになりました。
このように、当センターは、時代の変化に合わせて組織の形を変えながら活動を続けて参りましたが、今、世界はこれまでにない大きな変革期を迎えております。特に、看護をとりまく医療・介護分野では、次々とイノベーションが生まれ、看護職には、人々の持つ多様な力をテクノロジーと結びつけ、個人および社会のwell-beingを実現する、これまでになかった役割の発揮が求められるようになってきています。このような急激な環境変化に創造的に適応し、臆せず、柔軟な発想で新たな看護の役割を果たすことのできる次世代の看護職育成に向け、当センターでは、2024年度から、全国の看護系大学教員の「次世代育成力」を重層的に強化するレベル別体系的FD研修プログラムをスタートさせました。
今後も、当センターを利用してくださる皆様が相互に響き合いながら、惑うことなく創造的な取り組みを続けていくことを支援する拠点でありたいと思っております。皆様のご活用をよろしくお願いいたします。
センター長
和住 淑子
ページへ移動する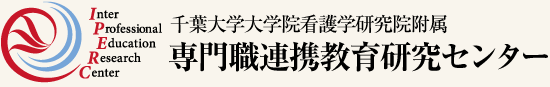
2015年(平成27年)1月1日、当センターは、初代、酒井郁子センター長のもと、日本では他に類を見ない新しいスタイルの教育・研究・実践拠点として開設されました。これまでの第1フェーズでは、「亥鼻IPE(Interprofessional Education)」という千葉大学亥鼻キャンパスを中心とした教育・学習プログラムの充実を目指し、その取り組みから得た知見を広く発信することを通して、日本の保健医療福祉及び高等教育の発展に尽力してまいりました。
私たちの取り組みは保健医療福祉の領域や日本国内に限るものではありません。令和4年(2022年)度に文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」の一つとして「 グローバル地域ケアIPE+創生人材の育成(Global & Regional Interprofessional Education Plus Program:GRIP Program)」に採択されました。GRIPでは、持続可能な開発目標(SDGs)の「目標3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」ことを目指して、あらゆる国・地域において、自国でも他の国でも健康関連の社会課題に保健医療福祉も含めた専門職者がともに取り組み、そこでの最適解を導き出すことができる自律した組織人の育成にも取り組んでいます。
今、多くの組織において、すべての構成員の人権が差別されることなく尊重され、一人一人の個性と能力を十分に発揮することができ、安心して所属できることが目指されるようになり、DEIB、すなわち多様性(Diversity)・公正性(Equity)・包摂性(Inclusion)・帰属(Belonging)の視点に立った様々な取り組みが行われています。千葉大学でも、令和6年(2024年)度に 千葉大学DEIB(C-DEIBシーディーブ)推進宣言及び基本方針を策定しました。
これからの第2フェーズでは、保健医療福祉や組織を超えた専門職連携教育IPE・専門職連携実践IPCP(Interprofessional collaborative practice)を、日本国内はもとより、世界のあらゆる国・地域・組織を超えてDEIBを実現する方法論と位置づけます。これらの方法論が広く社会で実装されるよう、第1フェーズでの原点「亥鼻IPE」を大切にしながら、当センターの歩みを進めてまいります。
専門職連携教育研究センター長
諏訪 さゆり